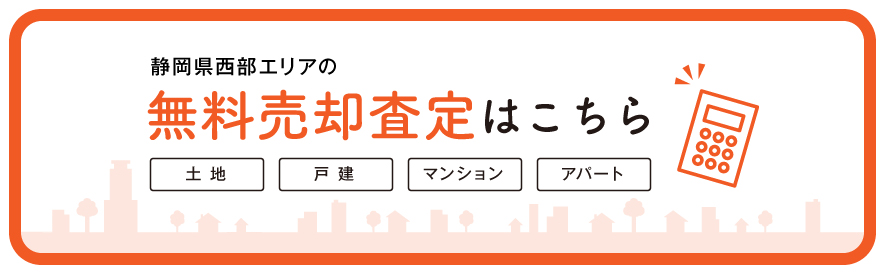登記事項証明書という言葉を聞いたことはあっても、具体的にどのような書類なのか、よく分からない方も多いのではないでしょうか。
登記事項証明書とは、土地や建物に関する重要な情報が記載された書類のことです。
不動産の売買や相続などさまざまな場面で必要となります。
本記事では、登記事項証明書に記載される内容や取得方法、登記簿謄本との違いなどを詳しく解説します。

遠鉄の不動産・中遠売買ブロック長 岸本 圭祐(きしもと けいすけ)
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、カラーコーディネーター、ファイナンシャルプランナー3級
登記事項証明書とは?

登記事項証明書とは、不動産の登記簿に記録されている内容の全部または一部を証明する書面です。
土地や建物の過去が記載された履歴書と考えるとわかりやすいでしょう。
不動産を売買するときや相続するとき、住宅ローンを融資してもらうときなど、さまざまな場面で登記事項証明書が必要となります。
登記事項証明書は、以前は登記簿謄本といわれていました。
データ移行できないものを除いて、2008年に全国の登記簿がコンピューター化され、紙による管理ではなくなったため、登記事項証明書と呼ばれるようになったのです。
登記簿がコンピューターで管理されるようになったことで、申請さえすれば全国の法務局で登記事項証明書を交付してもらえるようになりました。
そもそも不動産登記とは?
不動産登記とは、土地や建物にある権利関係を明確にするための手続きです。
不動産登記をすると、登記簿に以下の内容が記載されます。
- 土地や建物の所有者
- 土地や建物の抵当権の有無・抵当権の権利者
- 地積(土地の面積)
- 建物の種類(居宅・共同住宅・店舗・事務所など)
- 建物の構造(木造・鉄筋コンクリート造)
- 建物の床面積 など
抵当権とは、住宅ローンを融資する金融機関が不動産を差し押さえられる権利です。
住宅ローンを返済する人が、一定期間返済を滞納した場合、金融機関は抵当権を行使して担保としている不動産を競売にかけます。
不動産登記をして記録された情報は、一般に公開されるため手数料を支払えば誰でも閲覧が可能です。
不動産の登記簿謄本と登記事項証明書とは違う?
登記簿謄本と登記事項証明書は、基本的に同じ内容が記載されていますが、厳密には異なる意味合いを持ちます。
- 登記簿謄本:紙の登記簿の写し
- 登記事項証明書:登記データをもとに発行される書類
紙の登記簿の写しが「登記簿謄本」
謄本とは、原本の内容が書き写されたり複写されたりした文書です。
登記簿謄本とは、登記記録が記載されている登記簿を複写した書類を指します。
登記簿が紙で管理されていた時代は、登記されている内容を証明する際に原本の写しが交付されていました。
登記データをもとに発行されるのが「登記事項証明書」
登記簿は2008年に電子化され、登記記録というデータで管理されるようになりました。
登記簿が電子化されたことで、登記されている内容を証明する際は、登記記録情報を印刷が可能となったのです。
印刷された書類は、厳密にいうと謄本ではないため、登記事項証明書と呼ばれています。
登記事項証明書(登記簿謄本)の記載事項
登記事項証明書(登記簿謄本)の記載事項は、主に以下の4つです。
- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
- 共同担保目録
画像引用:法務省「全部事項証明書(不動産登記)の見本」
表題部
表題部は、土地や建物の所在地や状態などが記載される部分です。
土地の場合、表題部に記載されるのは、地番や地目(どのような土地であるか)、地積(土地の広さ)などです。
建物の場合は、家屋番号や種類(建物の用途)、構造、床面積などが記載されます。
権利部(甲区)
権利部には、不動産の権利関係が表示されます。
甲区に記載されるのは、所有権保存登記や所有権移転登記など不動産の所有権に関することです。
また所有者の住所や氏名、取得日なども記載されており、権利部(甲区)を見るといつ誰がどのように不動産を取得したのかがわかります。
権利部(乙区)
権利部の乙区に記載されるのは、所有権以外の権利に関することです。
抵当権や地上権、根抵当権、賃借権などの移転や抹消については乙区に記載されます。
共同担保目録
共同担保目録には、債権の担保になっている不動産が一覧で表示されます。
住宅ローンを組んで不動産を購入するときは、建物と土地の両方が担保となるため、共同担保目録には土地と建物が記録されます。
登記事項証明書の種類
登記事項証明書には、以下の4種類があります。
- 全部事項証明書
- 現在事項証明書
- 一部事項証明書(何区何番事項証明書)
- 閉鎖事項証明書
全部事項証明書には、閉鎖されたものを除いて登記簿に記録された事項の全部が記載されています。
現在事項証明書に記載されているのは、登記簿に記録されているもののうち、請求時点で効力を有している事項です。
一部事項証明書とは、 登記簿に記録された事項のうち、特定の部分だけを参照できる登記事項証明書です。
マンションや複数人で共有する土地など、権利関係が複雑である不動産の全部事項証明書を取得してしまうと、ページ数が膨大になってしまいます。
そこでマンションや複数人で共有する土地などの登記事項証明書を取得する際は、一部事項証明書を申請すると発行枚数を少なくできるのです。
閉鎖事項証明書には、閉鎖された登記記録が記載されています。
建物の滅失や土地の合筆など、すでにない登記情報は、全部事項証明書や一部事項証明書などには記載されないため、閉鎖事項証明書を請求する必要があります。
登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書の取得方法は、以下の3種類です。
- オンライン
- 窓口
- 郵送
上記のなかでもおすすめなのは、オンラインによる請求です。
オンライン請求は、インターネット環境があれば、自宅や勤務先などから請求できるだけでなく、手数料も安く抑えられます。
なお登記事項証明書を入手する際、認印や身分証明書を準備する必要はありません。
オンラインでの取得方法
登記事項証明書は、インターネットから登記供託オンラインシステムにアクセスし、所定の手続きをすると請求できます。
オンラインで請求するためには、事前に利用者登録が必要です。
利用者登録が終了したら、不動産の情報を入力して送信すると請求できます。
オンラインで請求した登記事項証明書は、自宅や勤務先などに郵送してもらえるほか、最寄りの登記所や法務局で受け取ることも可能です。
法務局の窓口で登記事項証明書を受け取る場合でも、事前にオンラインで請求手続きをすればスムーズに交付してもらえます。
オンラインで登記事項証明書を取得する際の手数料は以下のとおりです。
- 自宅や会社になどへ郵送:1通につき500円
- 法務局での受け取り:1通につき480円
手数料は、インターネットバンキングの電子納付で納めます。
またPay-easyに対応したATMでの納付も可能です。
ただしオンライン請求できるのは、全部事項証明書と現在事項証明書、閉鎖事項証明書の3種類です。
一部事項証明書はデータ化されていないため、オンラインで取得できません。
土日祝日や年末年始は、インターネット環境があってもオンラインで登記事項証明書の申請はできません。
なお平日の午後5時15分以降にオンライン申請した場合、翌営業日以降の受付となります。
窓口での取得方法
登記事項証明書は、最寄りの法務局に行って申請すると入手できます。
法務局で登記事項証明書を入手するためには、法務局に置いてある「登記事項証明書交付申請書」を記入しなければなりません。
法務局の窓口で申請する場合の手数料は、証明書1通につき600円です。
手数料は、収入印紙を購入し申請書類に添付して納めます。
なお収入印紙は、法務局で販売されているため、あらかじめ購入する必要はありません。
郵送での取得方法
登記事項証明書交付申請書を法務局へ郵送すると、 登記事項証明書を自宅や勤務先などに送ってもらえます。
郵送申請の手数料は、法務局での申請と同じく証明書1通につき600円であり、収入印紙を申請書に添付して納めます。
収入印紙は、郵便局やコンビニなどで購入が可能です。
郵送申請のメリットは、いつでも申請できる点です。
ただし郵送申請は、指定の場所に登記事項証明書が郵送されるまで時間がかかる場合があります。
木曜日や金曜日に申請書を郵送すると、自宅に証明書が郵送されてくるまで一週間以上かかる場合もあります。
登記簿謄本(登記事項証明書)の有効期限
ただし提出先によっては「取得から3か月以内」といった期限が設けられることがあるため、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得する前に確認をしておくと良いでしょう。
登記事項証明書を請求する前にやるべきこと

登記事項証明書を請求する場合、氏名や住所に加えて「地番」や「家屋番号」も記入する必要があります。
- 地番:土地の登記上の番号
- 家屋番号:建物の登記上の番号
地番や家屋番号は、固定資産税の納税通知書や課税証明書に記載されています。
不動産の住所と、地番や家屋番号が必ずしも同じとは限りません。
地番や家屋番号を事前に調べておくと、すばやく申請でき登記事項証明書をスムーズに交付してもらえます。
なお法務局で登記事項証明書を申請する場合、地番や家屋番号が分からければ法務局で尋ねることも可能です。
登記事項証明書の内容はオンライン閲覧もできる

登記情報は、登記事項証明書を請求しなくてもインターネット上で閲覧が可能です。
登記情報を閲覧したい場合は、一般財団法人民事法務協会が運営する「登記情報提供サービス」にアクセスしましょう。
登記情報提供サービスの利用方法は、利用者登録をして登録する「個人利用」と、利用者登録をせずに利用する「一時利用」の2種類です。
登記情報提供サービスでは、登記情報を閲覧するたびに利用料金がかかります。
利用料金は、クレジットカードで支払います。
個人利用の場合は、登録料として300円が必要です。
一時利用は個人利用とは異なり登録料はかかりませんが、利用するたびに氏名やログインパスワードを登録し、利用者IDを取得しなければなりません。
サービスを利用できる時間は、平日の午前8時30分〜午後9時までであり、土日祝日や年末年始は利用できない点に注意しましょう。
なお登記情報提供サービスで閲覧できるのは、基本的に全部事項証明書のみです。
またサービスで検索した登記事項証明書を印刷しても、公的な証明書として扱われません。
登記簿謄本(登記事項証明書)に記載された所有者の変更方法
登記簿謄本に記載されている所有者を変更するときは、法務局で所有権移移転登記をする必要があります。
所有権移転登記は、自分自身でもできますが法律や不動産の専門知識が求められるため、報酬を支払って司法書士に依頼するのが一般的です。
また所有権移転登記をする際は、登録免許税という税金を支払わなければなりません。
【まとめ】登記事項証明書は不動産取引に欠かせない書類
登記事項証明書には、不動産の所在地や権利関係、所有者、地積・床面積などの重要な情報が記載されています。
登記事項証明書を取得するときは、法務局の窓口、郵送、オンラインのうち利用しやすい方法で請求をするとよいでしょう。
請求する際は地番や家屋番号が必要となるため、固定資産税の納税通知書や課税証明書で事前に確認しておくとスムーズに請求できます。
(執筆者:品木 彰)